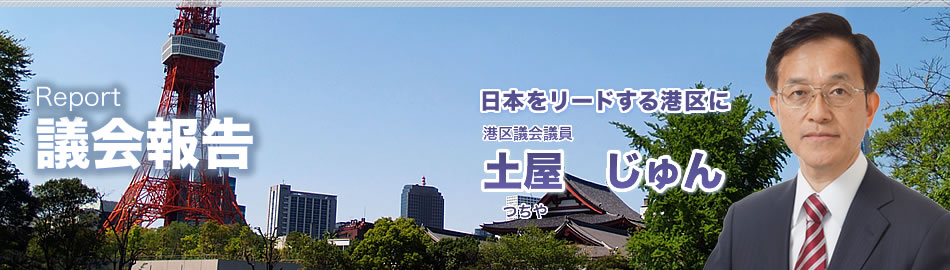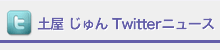○委員(土屋準君) それでは、令和5年度決算特別委員会に当たり、自民党議員団を代表して総括質問をさせていただきます。
今回の決算特別委員会は、令和5年度の決算の審議ではありますが、武井区政20年の実質的な最終年度になると思いますので、この20年を振り返りながら質問したいと思います。
初めに、港区基本構想と港区基本計画についてです。
款別審議でも取り上げましたが、区長は基本構想の見直しを掲げていますけれども、実際の区政は基本計画を指針として運営されていると思います。よって、区政運営の上では、この基本計画の改定が重要になってきます。それならば、いっそ基本構想を基本計画に組み込んで、新・基本計画として策定してはどうかと思います。
また、計画期間については、平成15年に港区基本計画を作成した際に6年とし、3年目に見直しを行っており、その後、平成21年に地区版計画書を新たに策定し、現在の計画の仕組みとなっております。
現行の港区基本計画は、計画期間の中間年である3年目に見直しを行うことで、変化の早い社会動向の中でも、直面する課題に対して的確に施策を講じることができる一方で、他自治体と比較しても見直し期間が短いため、改定作業に必要となる職員や費用の負担は大きく、また、計画の達成状況を評価する政策評価の際には、対象となる期間が短いため、今後の見通しを立てづらいといった課題があります。
政治過程の観点からすれば、計画の期間は区長の任期である4年とすべきではないかという考え方があります。選挙により区民の信託を受けた区長が、公約実現のため基本計画を策定すべきであって、そのためには計画の期間は区長の任期に合わせるべきではないかというものです。そこで、中間の見直しをしない代わりに期間を4年とする案も考えられます。一方、計画期間のサイクルは継続的なもので、区長の任期に合わせるのはタイミングが難しいという問題も考えられます。
そこで質問は、基本構想を基本計画に組み込んで、新・基本計画として策定することについて、どのように考えますでしょうか。また、基本計画の期間を4年とすることについて、どのように考えますでしょうか。
次に、東京湾大華火祭の再開についてお伺いをいたします。
東京湾大華火祭については、平成27年8月8日を最後に開催されていません。一旦休止となった理由は、中央区晴海にある花火観覧のメイン会場が、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村として整備することとなり使用できなくなったことが大きな理由です。我々自民党も、休止直後から、都議会議員などとも協力して再開に向けての方策を模索してきましたけれども、中央区は休止以降も再開に向けての方策を現在に至るまで模索しており、武井前区長が在任中から、港区は中央区との協力関係を築いておりました。清家区長に替わってから積極的に関わり始めているわけではありません。
現在、中央区は、東京湾大華火祭再開に当たり、令和4年度に基礎調査を行い、調査結果に合わせて、港区等、近隣区との調整を進めることが重要であるとしています。基礎調査では、必要経費が総額で約7億9,800万円かかるとしており、物価や人件費が高騰している昨今では、さらなる経費の増加が予想されます。これについては、これまでの質疑の中でも述べましたけれども、ふるさと納税を活用したり、開催時期をずらすなどして工夫することも考えられます。我が会派としましても、東京湾大華火祭の早期の再開を望むところではありますけれども、想定される様々な課題に丁寧に向き合い、着実に取り組むことが重要であると考えております。
そこで質問は、東京湾大華火祭再開に向け、区は今後、中央区との検討をどのように進めていくのか、お伺いします。
次に、区役所・支所改革についてお伺いします。
武井区政20年の振り返りで、区政の大きな転換をもたらしたのは、区役所・支所改革だと思います。平成18年4月に行われた区役所・支所改革により導入された総合支所制度は、港区の大きな特徴となっております。それにより、より便利で、より身近な区政が行われるようになりました。区への申請・相談は原則として地区の総合支所で受け付けられ、町会・自治会などのほか、その地区で活動する企業、NPO、ボランティアなど多様な団体や個人との協働による地域活動の支援などの充実がなされました。さらには、地域の区民の声を把握し、地域の区民等との協働により地域における独自の計画づくりが実施されるという、従来にはなかった新しい機能を持つようにもなりました。
現在の総合支所制度においては、日頃から地域の課題に向き合っている総合支所長が、地域の実態を政策形成に反映できるよう、支援部長を兼務しております。それに対して、総合支所長は兼務ではなく専任化させるべきではないかという意見もいただいています。
そこで款別審議では、部長級職員を増員するか、あるいは部長同士を兼任させるかといった、総合支所長を専任化させる場合の方法について質疑させていただきました。答弁では、部長級のみでなく課長級も含めた管理職全体の配置の視点も合わせて、より効果的・効率的な体制について検討するとのことでした。そうすると、総合支所長をそれぞれの管理課長などと兼任させれば、部長級は増えても課長級はその分減り、管理職全体の数は増減しないということになるのかもしれません。
そこで質問ですが、総合支所長専任化についてどのように考えるか、お伺いします。
次に、事務事業評価による財源確保についてお伺いします。
区長は選挙時に「事業の費用対効果と進捗管理の徹底見直しで、約50億円財源確保」を掲げていました。しかしながら、施政方針では50億円と述べていないことから、我が会派の池田議員が、第2回定例会の代表質問の際に、50億円の確保について具体的な費用対効果に基づいているか、進捗管理のプロセス、取組などの疑問点を挙げて問うたところ、50億円は令和6年度一般会計の2.7%に当たることを挙げ、事務事業評価に基づく見直し、新たに各所管と事業の進捗や課題を共有する場を設けることと答弁しました。
そうしたところ、今定例会の二島議員の代表質問に対しては、予算の削減ありきではなく、との答弁になり、そして再質問には、50億円という数字ありきではなく、との答弁になっております。区長に投票された多くの方が、当時の清家区長候補の、現在の港区が行っている事業の無駄に切り込んで新たな財源を捻出するという訴えに大いなる期待をしていたのではないかと思います。
そこで質問ですが、50億円の財源確保について、区長は一体どうしたいのか、それとも取り下げるという認識でよろしいのか、お伺いします。
次に、指定管理者への職員派遣についてお伺いします。
清家区長は、施政方針で「民間企業等との人材交流を推進」を掲げました。区長就任前から、URやJRなどとの職員の往来はありましたけれども、清家区長の下で一層進められていくことになるのではないかと受け止めております。ただ、どの企業に職員を送り、どの企業から職員を受け入れるか、区にとって、あるいは区職員にとってどのようなメリットがあるのか、公平性に問題はないか、民間企業等の選定には慎重な検討が必要と考えます。
そこで、区職員の派遣先として、指定管理者に指定された事業者は考えられないかと思います。区は、港区指定管理者制度運用指針において、区と指定管理者の関係を、業務委託のように発注者と受注者として区が一方的に業務内容を提示し、指定管理者を指導・助言する関係として捉えるのではなく、指定管理者を共通の目標の達成を目指すパートナーとして捉え、連携・協働しながら、サービスの質の向上と安定的な提供に取り組むと掲げております。
しかしながら、それと裏腹に、施設の運営・管理が指定管理者に丸投げになっているのではないか、それにより区職員の現場感覚が失われているのではないかといった問題提起がなされております。
元麻布保育園の指定取消しという重大な事態も生じていますが、そこまで大ごとではなくても、毎年度行われている財政援助団体監査で不適切な事務処理が度々指摘されております。
そこで、例えば、次期選考に関わらない指定期間の前半の一、二年間、共通の目標を共有するパートナーである指定管理者に区職員を派遣し、区職員が利用者へのサービスの最前線、あるいはそのバックオフィスで施設管理に関わり、指定管理者による施設運営を軌道に乗せていく、そうした役割を担うことは、適切な施設管理はもちろん人材育成にも資すると考えられます。
Kissポート財団に対しては、区民センターや伝統文化交流館の指定管理者でありながら、区職員の派遣を行っており、制度的にできないということではないと考えております。
そこで質問は、指定管理者に区職員を派遣することについてどのように考えるか、お伺いします。
次に、女性管理職の割合についてお伺いします。
款別審議でも取り上げましたが、区長は、女性管理職の割合50%実現を目指し、任期4年間での達成を目指すとしています。
審議の中では、管理職ポストをその分増加させることはできるのか、内部から女性のみを昇進させることができるのか、また、例えば女性であることを条件として任期付職員を公募するといったことはできるのか、4年間で男性の管理職をその分外部に放出し、女性のみ新たに外部から登用することはできるのかといった方法について質問しましたが、答弁を聞きますと、どれもなかなか達成が難しいと感じました。
女性が働きやすく、キャリアアップを望める環境を整えていくのは当然ですが、それで4年間で50%実現は難しいですし、民間専門人材等で新たなポストを設置することを含めて取組を検討するとのことですが、ポストは業務上必要が生じるなどして設置するもので、50%実現を達成するために設置することになるのは本末転倒な話です。
そこで質問は、この目標をどのようにして達成するのか、お伺いします。
次に、女性活躍推進と性的少数者への配慮についてお伺いします。
これも款別審議でも取り上げましたが、審議会委員や職員の履歴書等の性別欄の男女別記載はどのようにされているのか、質問をしました。
答弁では、審議会等における公募委員の選考や職員の採用選考においては、性別欄は設けていないか任意記載としているとのことでした。一方、団体推薦の審議会等委員については、推薦元の団体に女性の推薦について協力を依頼することがあり、審議会等委員の委嘱後には男女を確認、職員についても任用時には任用履歴書に性別欄を設け、男女を記載しているとのことでした。
女性活躍推進の立場からすれば、公職の候補者や審議会委員、管理職員の女性の割合を高める目標を設定するのであれば、男女の区別を明確にする必要がありますが、性的少数者に配慮する立場からすれば、男女の区別を明確にしないということが起こります。
そこで質問ですが、女性活躍推進と性的少数者への配慮について、どちらを優先するのか、お伺いします。
次に、住民票における同性カップルの表記についてお伺いします。
これも款別審議で取り上げましたが、長崎県大村市が、同性カップルの住民票で、世帯主と同居するパートナーの続き柄欄に「夫(未届)」と記載するということがありました。住民票は、住民の届出などに基づき区市町村がつくりますが、自治体ごとにばらばらにならないよう、住民基本台帳法で項目などを規定し、実務は総務省が技術的助言としてまとめた要領に基づいてつくられています。総務省は、令和6年9月27日に改めて、長崎県大村市に対して、実務上支障のおそれがあるとの見解を示した上で、全国の自治体に送付し、大村市には事務処理の再考を求める文書を送付したとのことです。
そこで質問は、同性カップルの住民票の届出依頼について、どう対応するのか、お伺いします。
次に、港区平和都市宣言についてお伺いします。
今定例会の二島議員の代表質問に対して、区長は、文言の追加や変更については考えていないとの答弁でした。一方、刊行物への掲載については、宣言を掲載する刊行物や掲載方法について再検討するとともに、デジタル技術を活用した新しい手法について検討していくとのことでしたが、再検討により外すこともあり得るのかという再質問には、どのような媒体に掲載するのか、今後検討していくとのことでした。
また、款別審議の際には、港区平和都市宣言がより広く効果的に区民に伝わるよう改めて検討した結果、刊行物については10月から、基本構想や基本計画・実施計画、各個別計画のような構想、計画に当たる冊子、また、平和事業において発行する冊子に限定して掲載することとするとの答弁がありました。
そこで質問は、刊行物への掲載、あるいは削除に当たっての基準はどのようなもので、その理由はどのようなことによるものなのか、お伺いします。
次に、区政運営と町会・自治会の認識についてお伺いします。
港区は、多様な人々が集まり、伝統と先進性が共存するまちとして発展してきました。その発展の礎となっているのが、町会・自治会の存在です。町会・自治会は、地域の安全や福祉の向上、災害時の支え合いなど、住民が安心して暮らせる環境を整える上で欠かせない役割を果たしています。地域社会のつながりが希薄化する現代において、町会・自治会は、地域コミュニティーの絆を強め、未来へとつなぐ重要なパートナーです。
そこで4点質問します。
区長は、これまでの港区政のように、町会・自治会を地域における区政協働の最上位団体として位置づけていくのか、明確にお答えください。
町会・自治会の活動をさらに活性化させるために、具体的にどのようなビジョンをお持ちでしょうか、お伺いします。
区政との地域連携の基礎単位として機能するのは町会・自治会であり、マンションの自治会も地域の町会としっかり連携できることが前提であると考えます。このような従来の在り方が地域発展と絆づくりのために望ましいと考えますが、区長はこの点についてどのようにお考えでしょうか。
町会・自治会とマンション住民の連携を強化するために、どのような施策をお考えでしょうか。
以上4点、お伺いいたします。
次に、防災についてお伺いします。
第2回定例会で、我が会派の池田こうじ議員が取り上げましたが、港区は、地域防災計画を改定し、6年後の2030年度までに首都直下地震等の被害をおおむね半減させることを目指しています。ところが、区長は、これを3年で被害をおおむね半減させると言っていますので、さらに改定するということになります。ところが、区長の答弁では、3年で被害をおおむね半減できる根拠が見受けられませんでした。
そこで質問は、どのようにして被害想定を3年で半減するのか、お伺いします。
次に、神宮外苑再開発についてお伺いします。
まず、区長のスタンスについてです。今定例会で我が会派のやなざわ議員は、区長は区議会議員時代に「神宮外苑再開発には東京都と対峙してでも反対しています」と主張していましたが、区長選挙に出馬表明するに当たり「説明会を求める」にとどめたことについて、区議会議員時代と区長選挙直前になってからではスタンスを変えたのかという質問をしました。
区長は、再開発に反対と掲げていたことはなく、再開発の計画の見直しをと言ったことの誤認かと思われるとの答弁でした。かつて「反対しています」と掲げ、その記録も残っていますが、「反対したことはない」ということは明らかに事実をねじ曲げているのではないかと思います。
そこで質問は、過去の立場と現在のスタンスが変わったのか、しっかりとした説明をお願いします。また、反対をしたことはないと答えたことから、今後も計画を止めるつもりはないということでよろしいのか、お答えください。
2つ目に、公共施設管理者同意についてお伺いします。
神宮外苑地区第1種市街地再開発事業の事業計画における公共施設管理者同意についてお伺いします。土木費の款において、我が会派の三田委員から次の質問を行いました。
すなわち、「神宮外苑地区第1種市街地再開発事業の事業計画に係る公共施設の同意について(回答)」について、新区長の下でも、行政の連続性を担保する観点から、今後も、本回答書の記載の事項について何ら変更は生じないものと理解してよろしいか、との質問ですが、これに対する所管課の答弁は、公共施設管理者同意については変わりないというものでございました。委員会の場での所管部門の答弁でありますので、当然、清家区長も同様の答弁となるはずかと思いますが、確認のため、区長からも答弁していただきたいと思います。本回答書に記載の事項について、何ら変更は生じないということでよろしいか、変更が生じるか生じないかで、どちらかで御答弁ください。
3つ目に、説明会の要請についてお伺いします。
区長は説明会を求めると言っていますが、説明会は武井前区長が求めていたので、結局同じなのではないでしょうか。款別審議の中でも、まだ十分な説明会が行われていない、再度要請を、との質問もありましたが、状況に応じて要請するとの答弁でした。
そこで質問ですが、今はどういう状況だと捉えているのでしょうか。また、今の状況だと、説明会はもう求めないということでよろしいでしょうか。お伺いいたします。
4つ目に、歴史的資源の改廃を制限することについてです。
神宮外苑のまちづくりが話題になってから、歴史的な資源を守ることを声高に主張される方が多く感じられます。新区長となって初めての定例会で、歴史的価値のあるものを守る仕組みづくりについての答弁で、専門家を交えた会議体により、新たな制度の構築に取り組む、と答えています。
ここで問題になるのは、話題に上がる歴史的価値のあるものは、公共施設ではなく、民有物であり、私有財産であるということです。所有者がいるわけで、本来他人が口出しできないものです。以前に、会派に対して西麻布交差点付近のマンション屋上の電子公告がまぶし過ぎるとの陳情がありました。これは御存じのとおり、区長の御家族所有のマンションです。高速道路を通行する車向けに設置された映像による広告で、フラッシュ的に明るくて、真夜中も照らされたら寝るどころではありません。しかし、行政側としても屋外の電子広告物を撤去しろなどということはできないのであります。それは財産権の侵害に当たるからです。大規模開発に対しても同じです。
憲法29条財産権では「これを侵してはならない」と規定されており、3項で「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」という例外だけを定めています。歴史的価値があるものを公共のために用いるわけではないなら、当然財産権を侵害してはなりません。
そこで質問は、これから清家区長が取り組む新たな仕組みづくりも、私権の制限を行わないものにすべきであると思いますが、区長のお考えをお伺いします。
次に、羽田空港機能強化についてお伺いします。清家区長は、区長就任後、区議会議長と一緒に国土交通省へ羽田空港機能強化の問題について要請に行ったそうです。しかしながら、区長は国土交通省の担当者に対して、自分の家の上空をジェット機が飛んでうるさいとかの話しかできずに、あきれ果てた区議会議長がこれまでの区議会の意思を伝えて、その場をしのいだと聞いております。
しかし、区長はもともと、みなと政策会議という会派におられたわけですが、そのときの区長の行動は、みなとの空を守る会とともにあり、着陸方法の変更や地方空港の活用等による固定回避を要請する武井区政とは相当距離があったと記憶しております。
改めて聞きますが、みなとの空を守る会などとともに、港区上空を飛ぶ旅客機はすぐに飛ぶのをやめさせたいのか、それとも、国土交通省とのやり取りの中から生まれた、着陸方法の変更や地方空港を活用するなどの固定化回避に向けた行動とするのか、はっきりと区長としての考えを示すべきであると考えます。かつての反対の姿勢から変わったのであれば、はっきりとこの場で表明をしていただきたいと思います。
そこで質問は、区長はかつての反対の姿勢から変わったのか、お伺いします。
次に、「ちぃばす」の今後の取組についてお伺いします。
武井区政20年を振り返りますと、港区コミュニティバス「ちぃばす」の運行拡大が大きく進んでまいりました。「ちぃばす」は、平成16年に2路線で運行を開始、平成22年に新たな5路線を導入、合計7路線で運行され、区民や在勤者に親しまれています。しかし、最近は、バス業界全体で運転士不足が深刻な問題となり、運行を担当するフジエクスプレスでは、数年前から採用活動や労働環境の改善に取り組んでいるようですが、運転士の確保が困難になり、麻布東ルートが一部運休になっております。一方、最近では、ICTの発展もあり、スマートバス停などの取組も進められています。
そこで質問は、「ちぃばす」の運転士不足やICTの進展といった状況も踏まえ、今後の「ちぃばす」の改善についてどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
次に、2050年ゼロカーボンシティーの達成に向けた再生可能エネルギーの取組についてお伺いいたします。
武井区政20年の間には、地球温暖化防止に向けた取組も大きく進められました。港区は、地球温暖化防止に向けた取組として、平成19年度から約22ヘクタールの森林をあきる野市から借り受け、手入れが行き届かない荒廃した森を二酸化炭素の吸収林としてよみがえらせ、みなと区民の森として、環境学習の場としても活用しております。
平成23年度からは、二酸化炭素を吸収する国産木材の使用促進に加え、国内の森林整備にもつながる、港区と地方が連携して地球温暖化防止に取り組む、日本で唯一の、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度もスタートさせました。
令和3年には、2050年までに二酸化炭素を含む温室効果ガス排出実質ゼロを目指すことを表明し、都内初の取組として、区有施設で使用する電力を太陽光発電などの100%再生エネルギーに切り替える取組を推進しております。
令和6年2月改定の環境基本計画においては、ゼロカーボンシティー達成に向けて、2030年度には区内の二酸化炭素排出量を2013年度比で51%削減と高い目標を掲げており、これまでの取組を含めて、持続可能で快適な都市環境を次世代へ引き継ぐべく、積極的に進めていく港区の姿勢の表れであると考えております。
そこで質問は、再生可能エネルギーの導入に向けた今後の取組について、どのように考えるか、お伺いします。
再生可能エネルギーの導入拡大に向けては、港区だけの取組ではなく、技術力や実績などを持っている民間企業や他の自治体との連携が重要です。港区基本計画においては、参画と協働の取組を一層推進し、行政、区民、民間、そして全国各地域の4つの力を組み合わせ、港区の持つ総合力を生かした区政運営を展開するとしています。
令和5年10月には、みなと環境にやさしい事業者会議やエコライフ・フェアMINATOなど、港区の取組に参画してきた東京ガスと、脱炭素社会の実現等に向けた包括連携協力協定を締結し、脱炭素社会の実現に向けた取組を推進しています。
私は、これまでに築いてきた連携関係をより強固で継続的なものとすることで、地域社会のさらなる発展に貢献するものとして期待をしております。
武井前区長は、お互いの地域の発展と住民のより豊かな生活の実現に向けて、全国自治体との連携を強く進めてきた結果、その自治体数は令和6年6月時点で330に及んでいます。武井前区長が培ってきたネットワークを生かし、港区として引き続き様々な自治体と連携して、2050年ゼロカーボンシティーの達成に向けて取組を推進していくべきと考えます。
そこで質問は、全国連携の強みを生かした今後の取組について、どのように考えるか、お伺いします。
次に、プレミアム付き区内共通商品等の産業振興施策についてお伺いします。
区内共通商品券の発行支援は、武井区政における産業振興施策の大きな柱だったと思います。共通券・限定券の2種類の券種の取扱いや、プレミアム率、発行額など、大きな進展を遂げてきました。一方、最近では、電子商品券やアプリ化など、新たな進展も見られます。
そこで質問ですが、プレミアム付き区内共通商品券をはじめ、今後、港区電子スマイル商店街アプリを活用した産業振興施策にどのように取り組んでいくのか、お伺いします。
次に、港区社会福祉協議会への支援についてお伺いします。
1つ目は、社会福祉協議会の体制強化を支援することについてです。
我が会派の三田議員の一般質問での、身寄りのない高齢者の身元保証に関する支援の実現を訴えた質問に対し、清家区長からは、入院時や施設入所時の保証機能や死亡時の葬儀、埋葬などの手続の支援について、実施に向けた検討を加速するとの答弁がありました。文字どおり、早期の実現に向けて検討を加速してほしいと思いますが、検討の担い手、事業の担い手となる社会福祉協議会の体制には十分配慮が必要です。
社会福祉協議会では、本年4月に、ひきこもり支援専用相談窓口を開設しましたが、窓口の認知度が高まり、相談件数が増えるにつれ、孤独・孤立の問題への対応にかかる社会福祉協議会の役割は、今後ますます重みが増していくことと思います。
また、来年度以降、社会福祉協議会は、重層的支援体制整備事業の担い手として、複雑な福祉問題を一つ一つ解決に導いていくための高度な調整力が求められることになります。同じく一般質問で利用促進を求めた任意後見制度や、法人後見の取組に対する期待にも、成年後見制度の中核機関として応えなければなりません。
そのためには、職員の増員や専門職の確保など、必要な体制をしっかり整える必要がありますが、区の財政支援がなければそれもままなりません。港区社会福祉協議会が万全の人員体制の下で仕事に臨み、地域福祉の担い手としての役割を全うできるよう、区は、社会福祉協議会の体制強化を促し、支援すべきと考えます。
そこで質問は、社会福祉協議会の体制強化を支援することについて、どのように考えるか、伺います。
2つ目は、港区社会福祉協議会に区職員を派遣することについてです。
総務費の質疑では、外郭団体に対する区の関与の在り方を見直していくという答弁がありました。一定の緊張感と距離感の中で、外郭団体の指導監督を行うという区の役割は大切だと思いますが、一方で、地域福祉の推進という同じ目的を共有する組織間での連携を深め、ともに歩むという考えに立てば、港区社会福祉協議会に区職員を派遣し、港区社会福祉協議会から区の福祉部門に職員を受け入れるといった総合交流は、双方の人材育成にも資するものと考えられます。
そこで質問は、港区社会福祉協議会に区職員を派遣することについて、どのように考えるのか、お伺いします。
次に、特別養護老人ホームについてお伺いします。
武井前区長は、長年にわたり、誰もが安心して住み続けられる港区の実現に向けた施策に取り組んできました。その中でも、要介護者の増加を見据えた特別養護老人ホームの整備があります。武井前区長が就任した平成16年6月当時、区内の特別養護老人ホームの定員は合計410名でしたが、就任後、平成18年5月の新橋さくらの園の開設を皮切りに、平成22年3月には、きのこ南麻布と洛和ヴィラ南麻布を、令和2年3月には、南麻布シニアガーデンアリスを順次開設させ、区内特別養護老人ホームの定員は倍増し、計829名まで増加してきました。
要介護者やその家族の思いに応えるため、また、そうした方々の人生に寄り添うために取り組んでこられた特別養護老人ホームの充実は、今も残る大変貴重な財産となっております。来年、南青山一丁目に定員29名の特別養護老人ホームが整備されることもまた、武井前区長が取り組んでこられた事業の一つです。
残念ながら、区内特別養護老人ホームの一つ、定員51名の民設民営のベルが、本年6月末に経営難などを理由に廃止となったわけですが、区内の人口は引き続き増加する見通しであり、高齢者そして要介護者は今後もますます増加していく見込みです。
在宅介護を支えるサービスの種類や有料老人ホームなどの他の入所施設も増えている中、これまでと同様に特別養護老人ホームのニーズが上昇し続けるかは定かではありませんが、少なくとも、要介護の高齢者が増えていくことは明らかです。
清家区長は施政方針演説において、第2の施策として、誰一人取り残さない「健康・福祉・共生都市」の実現を掲げられましたが、この特別養護老人ホームの整備に関する内容には触れられておりません。武井前区長が推し進めてきた「誰もが安心して住み続けられる港区の実現」、そして、特別養護老人ホームの整備について、区長はどのように考えておられるのでしょうか。
そこで質問は、要介護高齢者の需要を踏まえ、新たな特別養護老人ホームの整備が必要と考えますが、どの程度の規模の施設をどのように整備していくお考えなのか、お伺いします。
次に、子育て政策についてお伺いします。
武井区政20年において、子育て施策は強力に推進されてきました。平成18年には、23区初となる、出産費用助成を開始し、平成27年には、2人以上の子どもが通園する場合第2子以降の保育料無料を23区初の事業として開始しました。待機児童が増えた平成29年には、待機児童解消緊急対策として、保育園の定員拡大に尽力し、令和元年から今年の4月まで6年連続で待機児童ゼロを継続してきました。昨年には、出産費用の上限を81万円まで引き上げ、今年は子育てひろばでのおむつとお尻拭きを設置するなど、武井区政では「子育てするなら港区」というスローガンの下、子ども・子育て政策に力を入れてきました。
清家区長も、今後、子ども・子育て施策に力を入れていくと思われます。そんな中、今年度に(仮称)港区こども計画を策定すると聞いております。
そこで質問は、(仮称)港区こども計画に区長の思いをどのように反映していくのか、お伺いします。
次に、児童相談所における相談体制の一層の充実についてお伺いします。
現在、都内23区では、東京都の児童相談所と区の児童相談所が設置されている状況にあります。児童相談所を設置していない区については、東京都が子ども家庭支援センターに東京都の児童相談所のサテライトオフィスを開設するなど、様々な児童相談体制が混在しています。各自治体の考えに基づく相談体制の整備を否定するものでありませんが、多様な児童相談体制が考えられる中、区は、児童相談所を開設することの意義と重要性を訴え、港区の子どもは港区が守るという強い信念の下、令和3年に児童相談所を開設しました。
平成28年の児童福祉法改正により、区が児童相談所を設置できるようになりましたが、これ自体、武井前区長が23区を牽引し、国への働きかけをリードするトップランナーの1人として尽力したことで実現したものと言っても過言ではありません。
現在、児童相談所は開設4年目を迎え、併設する子ども家庭支援センターをはじめ、地域の関係機関と連携しながら、大きな事故なく、児童虐待や非行、障害、育成など、児童に関わる様々な相談に応じています。児童相談所が相談を受理した件数は年々増加しており、令和3年度は1,261件でしたが、令和5年度は1,445件で、増加率は約1.15%となっており、複雑な家庭環境や対応困難な事例も多いと聞いております。
相談件数の増加や対応が困難な事例が増えると、当然のことながら、1人の職員が担当するケース数が増え、負担も大きくなります。組織全体で対応しているとはいえ、そうしたことが積み重なれば、一瞬の判断ミスから、虐待死亡事故などの重大事故が我が区においても起きる可能性はゼロではありません。
さらに、報道にあるような、いわゆるトー横に集まる児童への対応や、赤ちゃんポストの設置を表明している医療機関との連携の在り方など、大都市特有の多くの課題にも的確に取り組んでいく必要があります。
そこで質問は、武井区政が築き上げてきた児童相談所の相談体制を一層強固なものにし、港区から重大事故を絶対に起こさないようにするためには、今後も職員の手厚い配置等の体制整備や、専門性の向上に取り組む必要があると考えますが、特別区として児童相談所を設置したメリットを含めて、どのようにお考えかお伺いします。
次に、総合教育会議と教育大綱の策定について、区長に伺います。
平成27年、教育委員会制度改革が行われ、区長と教育委員会で構成される総合教育会議が設置されました。総合教育会議の設置により、区長が教育行政に果たす責任や役割が明確になるとともに、区長が公の場で教育政策について議論することが可能になったほか、区長と教育委員会が協働・調整することにより、両者が教育政策の方向性を共有し、一致して執行に当たることが可能になり、地域の民意を代表する区長と教育委員会との連携が強化されるようになりました。
総合教育会議では、予算や条例提案等に加え、保育や福祉等の区長の権限に関わる事項等について協議し、調整を行うほか、政治的中立性が求められる事項は別ですが、教育委員会のみの権限に属する事項についても、自由な意見交換として協議を行うとのことです。
こうした改革の一つとして、地方公共団体としての教育政策に関する方向性を明確化するため、地方公共団体の長は、総合教育会議における協議を経て、教育大綱を定めるものとされました。ただし、港区では、港区教育ビジョン、これは平成26年10月策定ですが、これをもって港区の教育大綱に代えることとされました。しかし、令和6年度で現行の大綱の対象期間が終了することから、令和6年度中に新たに教育大綱を策定する必要があります。大綱には、行政全体を担う区長としての教育行政に対する考え、思いを示すことになります。
そこで質問は、区長は総合教育会議の意見交換や教育大綱の策定に当たり、教育行政に対するどのような考え、思いを持っているのか、お伺いします。
次に、小中一貫教育についてお伺いします。
港区では、全ての区立幼稚園、小・中学校で幼・小中一貫教育を推進しており、中でも小・中学校の施設が一体、または併設する学校について、学校間の連携、協力を推進することによる教育効果を見込み、小中一貫教育校への移行を進めてきました。これまで、平成22年にお台場学園、平成27年に白金の丘学園、令和5年に赤坂学園が順次開校し、今年の御成門学園の開校をもって、施設一体、併設型小・中学校の小中一貫教育校への移管は完了しました。
こうした中、最近では、小中一貫教育よりも中高一貫教育を求める声も上がっています。一方で、小中一貫教育を進めるならば、むしろ海外の高等学校と連携し、港区立中学校を卒業したら海外の高等学校に進学できる道を開けないかという意見もあります。
そこで質問は、今後の小中一貫教育、中高一貫教育をどのように考えるのか、お伺いします。
次に、国際理解教育についてお伺いします。
港区はこれまで、他自治体に先駆けて、様々な国際理解教育を進めてきました。平成18年度には中学校に英語科国際を導入し、ネーティブティーチャーを配置、平成19年度には小学校に国際科を導入し、ネーティブティーチャーを配置したほか、オーストラリアへの港区小中学生海外派遣を開始しました。
以降、テンプル大学と連携した国内留学プログラム・異文化体験授業を開始、東町小学校や南山小学校に国際学級を設置、麻布小学校や六本木中学校に日本語学級設置、そして昨年には、放課後オンライン英会話教室を開始、日本語適応指導を業務委託化し、今年は幼稚園へのネーティブティーチャー派遣、そしてシンガポールへの海外修学旅行を開始しました。こうした取組は、他の自治体には類を見ないほどで、港区の大きな特色となっており、注目されているところです。
そこで質問は、今後の国際理解教育をどのように考えるのか、お伺いします。
最後に、区長の政治スタンスについて、4点お伺いします。
1つ目は、政策合意についてです。
これまでの質疑の中で、特定の政党との政策の確認・合意があったのかという質問に対し、区長は、ニュースについては把握していない、特定の政党と具体的な政策の確認・合意をした認識はないとの答弁でした。ところが、政党の側は、政党の後援会ニュースで、確認・合意したと書いております。
そこで質問は、合意したとする文書は虚偽であるという認識でよろしいのか。虚偽の記載をされたなら、訂正を求めることはしないのか、お伺いをいたします。
2つ目は、区長の退職金カットについてです。
これも、これまでの質疑の中で、区長の退職金カットの公約に関係し、これまで区長の退職手当の額の見直しについては、あらかじめ港区特別職報酬等審議会に意見を聞いていることから、諮問の有無について検討しているとの答弁です。しかし、法的に諮問が必要か否かはすぐ分かることだと思いますし、必要なければ、すぐに条例制定の準備に取りかかれるのではないでしょうか。
そこで質問は、特別職報酬等審議会に諮問の有無を検討するのはなぜか、お伺いいたします。
3つ目は、平和感と憲法改正についてです。
款別審議の中で私は、平和の概念について、次のように述べました。「私は、平和を守るには2つの方向のことが必要だと思います。1つは、こちらから戦争を仕掛けないということです。こちらから戦争を仕掛ければ、当然平和ではなくなります。もう一つは攻められないということです。こちらから戦争を仕掛けなくても、他国から攻められれば戦火にまみれることになり、平和ではなくなります。このような観点から現行憲法を見ると、一方の観点からのことは書かれていますが、もう一方の観点からのことは書かれていません。よって、このままでは平和は守れないということになります。憲法改正に当たっては、平和を守るのか、それとも憲法の文言を守るのか、どちらを選択するのかということになると思います」というのが私の意見でした。
さて、区民の方からも、区長がどのような平和観を持っていて、憲法改正にはどちらの立場なのかということを聞かれます。港区は平和事業にも取り組んでいるので、区長はその姿勢を示すべきであると思います。
そこで質問は、区長の平和観はどのようなもので、憲法改正はどちらの立場かお伺いいたします。
4つ目は、夫婦別姓についてお伺いします。
夫婦別姓制度の議論自体は国政に関することですが、区政にも影響のあることですので、取り上げたいと思います。夫婦別姓制度の議論は、夫婦の間のことについての議論が多いですが、子どもの観点からの問題提起もされております。すなわち、夫婦別姓は必然的に親子別姓になり、決め方によっては兄弟別姓になるということです。子どもは姓を選べませんので、意にそぐわないことになることもあり、発育上の影響も出るかもしれないというものです。
そこで質問は、子どもの観点からの問題提起についてどのように考えるのか、お伺いをいたします。
質問は以上です。答弁をお願いいたします。
○区長(清家愛君) ただいまの自民党議員団を代表しての土屋準委員の総括質問に順次お答えいたします。
最初に、港区基本構想と港区基本計画についてのお尋ねです。
まず、基本構想を基本計画に組み込むことについてです。港区基本構想は、新しい時代に向け、区の目指すべき将来像を掲げるものであり、その実現に向けて施策の方向性を示すものが港区基本計画です。少子高齢化が進み、社会が大きく変化していく激動の時代を乗り越えていくためには、現行の基本構想をアップデートし、短期的な視点ではなく長期的な視点から区政運営を未来へと推し進めていく必要があります。今後、基本構想と基本計画を一本化することも含めて、計画体系の見直しを行い、未来への確かな道筋を示す新たなビジョンを区民と一緒につくり上げてまいります。
次に、基本計画の見直し期間についてのお尋ねです。
現行の港区基本構想は、策定した平成14年から10年ないし15年後を展望しておりますが、目標年次を既に経過していることから、まずは新たな基本構想において見据えるべき年次について検討を進めてまいります。その上で、計画体系の再構築と合わせて、計画の見直し期間について、3年から4年に変更することも含めて検討を行い、職員や経費の負担軽減など、これまで以上に効果的かつ効率的に計画行政を推進できるよう改善を図ってまいります。
次に、東京湾大華火祭の再開についてのお尋ねです。
区は、中央区と東京湾大華火祭の再開に向けた実務的な協議を開始しております。中央区は、東京湾大華火祭は中央区の一大イベントであり、なるべく早期に実現したいとしております。区は、実務面での協議を段階的に進められるよう、再開に向けての課題などを中央区と共有しております。引き続き、東京湾大華火祭の再開に向け、積極的に取り組んでまいります。
次に、総合支所長専任化についてのお尋ねです。
総合支所制度が浸透し、地域との連携が深まる中、地域の顔として総合支所長に求められる役割も大きくなっており、総合支所長の在り方については検証が必要であると考えております。日頃から地域の課題に向き合っている総合支所長が支援部長を兼務することは、地域の実態を政策形成に反映できるという面もある中で、総合支所長をはじめ、様々な立場からの意見を聞きながら、専任化のメリット、デメリットを丁寧に検証し、区役所組織全体の総合的な観点から、より効果的、効率的な体制を検討してまいります。
次に、事務事業評価による財源確保についてのお尋ねです。
区は、事業の必要性、効果性及び効率性の観点による事務事業評価を実施しており、事業の見直しとスクラップ・アンド・ビルドの徹底に取り組んでおります。限りある財源と人員の中で新しい事業に取り組んでいくためには、不断の見直しが必要です。より効果的、効率的な区民サービスを提供できるよう、部署横断的に、総合的な観点から事業のあるべき方向性を検討し、全庁一丸となって、不要な経費の削減に徹底的に取り組み、財源確保に努めてまいります。
次に、指定管理者への職員派遣についてのお尋ねです。
指定管理者制度は、公の施設の管理に民間企業などが有するノウハウを活用することにより、多様化する住民ニーズに対応することを目的とするものであり、指定管理者制度の中で、区職員の派遣を受け入れるよう事業者に求めることについては、慎重な整理が必要です。一方で、公の施設の行政サービスを維持、向上させるためには、民間企業ならではの発想力や技術の習得、安定的な施設管理に必要な知見の継承など、区と指定管理者が丁寧に連携していくことは重要です。指定管理者への職員派遣につきましては、透明性や公平性を確保していく観点から調査・研究してまいります。
次に、女性管理職の割合についてのお尋ねです。
女性管理職の割合50%に向けて、女性管理職などによるキャリアアドバイザー制度などのこれまでの取組に加え、管理職になっても働きやすい環境の一層の整備や、昇任意欲のさらなる向上、民間人材の活用を進める中でのポストの増加など、様々な手法により、女性管理職の増員を目指していく必要があると考えております。
まずは今月中に、私と19名の女性管理職との対話機会を設け、現状の女性管理職が少ない原因についての分析、検討を行い、来月からは、若手職員とキャリアについて対話し、昇任やキャリア形成に向けての議論をするなど、女性管理職の割合50%実現を目指してまいります。
次に、女性活躍推進と、性的少数者への配慮についてのお尋ねです。
社会においては、男女間格差が依然として大きいことから、区の施策・方針決定過程に女性の意見を反映させるために、審議会等委員や管理職において女性比率の数値目標を定め、達成状況を毎年度把握しております。また、港区男女平等参画条例において、全ての人の性的指向、性自認及び性別表現が尊重され、誰からも干渉されず、侵害を受けないようにすることも定めております。女性活躍推進及び性的少数者への配慮について、いずれも区政の重要課題であると捉え、積極的に推進してまいります。
次に、住民票における同性カップルの表記についてのお尋ねです。
総務省の見解のとおり、同性カップルの住民票の続き柄を未届に変更した場合、実務上や制度上の課題があります。一方、区は、みなとマリアージュ制度を導入しており、当事者の心情に寄り添った表記ができるようにすることは、誰もが等しくサービスを享受することができる社会の実現につながるものと考えております。こうしたことから、今後、他の自治体と意見交換を行うとともに、国において、実務上や制度上の課題を整理し、当事者の心情に寄り添ったふさわしい表記となるよう要望してまいります。
次に、港区平和都市宣言の刊行物への掲載についてのお尋ねです。
総務費の審議において、担当課長から、港区平和都市宣言がより広く効果的に区民に伝わるよう検討した結果、掲載する刊行物を限定するとともに、並行して、デジタル技術などを活用した様々な手段によって区民に周知する旨、答弁いたしました。これは、港区平和都市宣言の認知度が低下している現状に鑑み、従来の方法にとらわれずに、区民に広く直接届く方法を積極的に進めていく区の姿勢を示したものであり、決して港区平和都市宣言を軽視しているものではありません。
40年前の区議会において、全議員が会派を超えて、核兵器の廃絶と人類の恒久平和を目指す、港区平和都市宣言を求める決議を提出し、全会一致で原案可決されました。これを受けて、世界の恒久平和と核兵器廃絶をうたった港区平和都市宣言を区が行ったことについて、私も真摯に受け止めており、歴代の区長と同じく尊重する姿勢に変わりはありません。
一方で、答弁後、刊行物への掲載ルール変更について、検討期間が短いことや、これまでどおり全ての刊行物への掲載を求める旨の御意見を、区議会や区民の皆さんから複数いただいております。御意見を踏まえ、刊行物への掲載の在り方については、改めて検討し直すことといたします。来年度実施予定の区民世論調査や、区事業におけるアンケートなど、様々な機会を捉えて、港区平和都市宣言の認知度や、宣言を知ったきっかけについて調査し、刊行物掲載による周知の効果を詳しく把握してまいります。
同時に、宣言を刊行物へ掲載するに当たって、刊行物そのものの趣旨が区民に伝わることも考慮しながら、宣言の効果的なデザイン、配置についても研究してまいります。様々な検討を尽くした上で、刊行物への掲載の範囲や方法について決定いたします。
来年度は戦後80年、平和都市宣言40周年の年です。40周年を契機に、港区平和都市宣言や、その趣旨をより一層区内に広く伝え、平和を希求する思いを区民と共有し、未来に受け継いでまいります。
次に、区政運営と町会・自治会の協働についてのお尋ねです。
まず、町会・自治会の位置づけについてです。町会・自治会の皆様方には、お祭りをはじめとした住民同士のつながりの創出や、災害時の助け合いを想定した防災訓練、地域の安全・安心のための防犯パトロールや清掃活動など、様々な活動に取り組んでいただいており、地域コミュニティーの根幹を担っていただいております。町会・自治会は、古くから地域活動の担い手として、また、区のパートナーとして港区を支えていただいている、最も重要な団体の一つであると認識しております。
次に、町会・自治会の活性化のためのビジョンについてのお尋ねです。
区は、町会・自治会を区政運営に欠かせない重要なパートナーと位置づけており、防災訓練などの住民の安全・安心に関わる取組や、お祭りをはじめとした地域のにぎわいの創出など、様々な取組を町会・自治会とともに進めていきたいと考えております。区では、これまでも職員がまちに出て積極的に声を聞き、相談に対応しておりますが、今後予定している町会・自治会へのアンケートの実施などにより、地域の課題を把握するとともに、必要な支援策を講じ、町会・自治会の活性化を推進してまいります。
次に、マンション自治会と、地域の町会・自治会との連携についてのお尋ねです。
地域のにぎわいを創出するための行事や防災に関する取組、清掃活動などは、地域全体で取り組むことにより、一体感が生まれることから、同一町会内のマンション自治会と町会・自治会同士が連携をして活動することは非常に大切であると考えております。また、令和5年3月の港区町会・自治会連合会設立により、地域を超えた交流や、町会・自治会同士の連携が図られるようになりました。町会・自治会とマンション自治会との連携についても、引き続きこの連合会の取組の中で推進してまいります。
次に、町会・自治会とマンションをつなげる施策についてのお尋ねです。
セキュリティーの高まりによって、地域の情報が届きにくいマンションが増加しており、町会・自治会と接点が持ちにくい住民も多いことから、町会・自治会とマンション住民との連携を深めるため、区が後押しをする必要があります。具体的な取組として、高輪地区総合支所では、町会・自治会とマンション管理組合などでプロジェクトチームを結成し、町会・自治会とマンションに対し、相互協力や交流促進の機会を提供しています。今後も、町会・自治会活動の魅力がマンション住民に伝わり、相互に連携するメリットを感じられる施策を推進してまいります。
次に、被害想定の半減目標についてのお尋ねです。
令和6年3月に港区防災会議が修正した港区地域防災計画では、東京都地域防災計画を参考に、防災・減災対策が強化された場合の被害低減効果を推計しており、耐震化の推進により、死者数、建物全壊棟数などの被害を6割から8割程度減少できることや、家具などの転倒・落下等防止対策実施率の向上により、死者数を4割から8割程度減少できる効果を見込んでいます。区は、港区地域防災計画で掲げた、被害想定を半減させる減災目標の達成に向け、耐震改修工事費用の助成による耐震化の推進や、家具転倒防止器具等の無償での支給による対策の実施などに取り組んでおります。
また、今年度から災害対策検討委員会に部会を設置し、マンション防災や、さらなる耐震化促進に向けた取組など、区の地域特性を踏まえた全国初の都市型防災モデルの構築に向けた、新たな取組の検討を進めております。こうした取組を着実に実行していくことで、区の防災対策がさらに加速化し、減災目標の早期達成が実現するものと考えております。
次に、神宮外苑再開発事業についてのお尋ねです。
まず、区長のスタンスについてです。私は、地域の人が大切にしてきた歴史や伝統が守られ、多くの人から理解や共感が得られる、対話をもって進めるまちづくりが重要だと考えており、一貫して住民との対話を求めてまいりました。神宮外苑再開発事業については、区及び東京都の都市計画審議会などの審議を経て、東京都が市街地再開発事業を認可しており、区長として賛成や反対を述べる立場にありませんが、事業者に対して、多くの区民等に共感が得られるまちづくりを行うよう強く求めてまいります。
次に、公共施設管理者の同意についてのお尋ねです。
区は、神宮外苑地区市街地再開発事業の事業計画に係る公共施設について、令和4年3月10日に決定した都市計画の内容と整合が図られていることを確認しております。また、イチョウ並木を中心とした景観への配慮や、イチョウ並木の保全について協議するよう条件を付しております。このため、協議回答書に記載の事項に変更は生じないと認識しております。
次に、説明会の要請についてのお尋ねです。区は、事業者に対し、本年7月に、広く一般に開かれた説明会の開催を再度文書で要請いたしました。その結果、本年9月に事業者が説明会を開催したことは一つの成果と認識しております。説明会については、今後も状況に応じて求めてまいります。
次に、歴史的資源の改廃を制限することについてのお尋ねです。
区は、地域に根づいた歴史的価値のあるものについては、地域のシンボルとして、広く区民に親しまれていることから、保全されることが望ましいものと考えています。一方で、これらの歴史的価値あるものの多くは私有財産であることから、処分や活用に当たっては、所有者の意向が優先されるものと理解しています。区は来年度、専門家を交えた会議体により、歴史的価値のあるものをこれからも所有者が保全し続けられるような、新たな制度の構築に向けて取り組んでまいります。
次に、羽田空港機能強化についてのお尋ねです。
羽田空港新飛行経路の運用が開始された令和2年3月以降、区は国に対し、令和4年度までは騒音対策や安全対策の強化などについて要請し、令和5年度以降は羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会及び住民説明会の早期開催等について要請を続けております。8月28日の国土交通省への要請の際には、新飛行ルート下における区独自の騒音測定の数値結果や、区民からの陳情などについて、区民の生活環境を守る立場から強く訴えてまいりました。今後も区は、国に対して、海上ルートへの変更も含め、新飛行経路の固定化回避に向けた検討を加速するよう要請してまいります。
次に、「ちぃばす」の今後の取組についてのお尋ねです。
区は、運転士の不足や、本年4月の労働時間などの基準改正に対応するため、運行経費の補助を通じて、運転士の負担軽減や雇用条件の改善など、運行事業者による採用や雇用継続の取組を支援しております。また、運行事業者とともに、「ちぃばす」のDX推進の一環として、ちぃばすナビの提供、スマートバス停の設置や、スマホ定期券の導入など、利便性向上に取り組んでおります。今後も区民の日常生活を支える地域公共交通としての役割を果たすため、運行事業者による運転士確保や、ICTを活用したサービス向上の取組を推進し、「ちぃばす」の安定的かつ継続的な運行に努めてまいります。
次に、2050年ゼロカーボンシティーの達成に向けた再生可能エネルギーの取組についてのお尋ねです。
まず、再生可能エネルギーの導入に向けた今後の取組についてです。
区は、区内で使用される電力の再生可能エネルギー割合100%を目指す再エネ普及促進プロジェクトを立ち上げ、区民や区内事業者の再生可能エネルギー由来の電力への切替えを促進しております。区有施設においては、これまで215の施設で再生可能エネルギー由来の電力を導入し、本年10月からは、新たな取組として、Jクレジットを活用した温室効果ガス排出実質ゼロの都市ガスを白金の丘学園に導入いたしました。今後も、さらなる再生可能エネルギーの導入促進に向け、区が率先して環境に配慮した電力やガスを使用することに加え、一般家庭や事業所における二酸化炭素排出量の削減に向けた取組を推進してまいります。
次に、全国連携の強みを生かした今後の取組についてのお尋ねです。
区は、これまでも全国自治体とのネットワークを活用した取組として、再生可能エネルギーの活用に関する協定を福島県白河市、青森県平川市、秋田県大仙市と締結し、現在区内13の公共施設に協定自治体で発電された再生可能エネルギー由来の電力を導入しております。本年7月には、自然エネルギーに触れる機会として、区内在住の親子21名に、福島県白河市の太陽光発電所を見学していただくなど、連携を生かした環境学習事業も実施しました。今後も、再生可能エネルギー資源を豊富に有する自治体と連携し、全国連携による脱炭素化に向けた取組をより一層推進してまいります。
次に、プレミアム付き区内共通商品券等の産業振興施策についてのお尋ねです。
今月1日に販売開始した電子商品券が既に約3,000万円使用されるなど、プレミアム付き区内共通商品券には区民などから高い関心が寄せられております。現在、さらなる商店街振興に役立つ電子商品券アプリの機能拡張を検討しており、電子マネーのチャージ機能や、アプリ決済に対する一定割合でのポイント還元、イベント参加などへのポイント付与機能を追加することで、ポイントが区内で循環するデジタル地域通貨の実現を目指してまいります。引き続き、港区商店街連合会とともに、商品券事業に加え、アプリ活用による商店街でのにぎわい創出に取り組んでまいります。
次に、港区社会福祉協議会への支援についてのお尋ねです。
まず、人員体制の強化に向けた支援についてです。
現在、港区社会福祉協議会との間では、重層的支援体制整備事業の実施や、ひきこもり支援の強化、いわゆる終活を支援する新たな仕組みの構築などに向けて精力的に検討、協議を重ねております。その中で想定される業務量や、それに見合う職員の数、従事する職員に求められる資格や経験など、具体的な内容について話合いを進めています。引き続き、社会福祉協議会との意思疎通を密にし、今後の事業展開に必要な人員体制の構築を積極的に支援してまいります。
次に、区職員を派遣することについてのお尋ねです。
区は、行政課題の解決に必要な知識、経験を有する人材の育成と、柔軟な発想や先進的な手法を取り入れ、組織の活性化を図るため、国や自治体、民間企業との人事交流などを行っております。区職員が、港区社会福祉協議会において、成年後見制度やひきこもり支援など、地域福祉における重要な役割を担い、ともに課題解決に当たることは、区職員の人材育成や社会福祉協議会の円滑な事業執行などにも寄与するものと考えております。今後、社会福祉協議会と意見交換しながら、区職員を派遣することについても検討してまいります。
次に、特別養護老人ホームについてのお尋ねです。
区では、特別養護老人ホームの計画的な整備を進めてきましたが、本年6月末のベルの廃止や、要介護者の増加などを受けて、さらなる施設整備が必要であると認識しております。コロナ禍後の入所申込者数の増加、施設運営における採算性の確保の観点などから、定員100名規模の施設が求められていますが、用地取得が困難な状況を踏まえ、小規模の施設を複数整備することも検討しております。今後、用地の積極的な取得のほか、これまでにない整備手法など、あらゆる可能性を視野に入れた検討を加速させ、特別養護老人ホームの整備に取り組んでまいります。
次に、(仮称)港区こども計画への区長の思いの反映についてのお尋ねです。
区は、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とする、(仮称)港区こども計画は、子ども、若者、子育て家庭など、幅広い世代を対象とし、子どもや若者が夢や希望を持てる施策を盛り込む総合計画として策定いたします。本計画では、新たな視点として、少子化対策につながる施策の明示や、子ども、若者、子育て家庭、それぞれに幸福度、満足度を測る成果指標を設定するなど、子どもと子育て家庭などが大切にされ、誰もが幸せを実感できる施策を効果的に推進できるよう工夫するとともに、その実現に向けて全力で取り組んでまいります。
次に、児童相談所における相談体制の一層の充実についてのお尋ねです。
区が児童相談所を設置し、子ども家庭支援センターをはじめ、区の様々な機関との連携、協同体制を強化したことで、それぞれの機能を生かした主体的かつ迅速な対応が可能となり、切れ目のない確実な支援につながっております。引き続き、国の基準を上回る職員を配置するとともに、医師や弁護士、保健師などの専門職との連携を一層図ることで、多角的な視点で相談に応じるノウハウを蓄積し、組織全体の専門性の向上に取り組んでまいります。また、現場とリアルタイムで情報共有などが可能なタブレットなど、ICTを活用した機動性のある支援に取り組むなど、全ての子どもと家庭が安全に安心して生活できる児童相談体制を構築してまいります。
次に、総合教育会議と教育大綱についてのお尋ねです。
今後、グローバル化や価値観の多様化が進む中、新しい技術を使いこなしながら自己の成長につなげるとともに、これまで以上に他者を理解し、思いやりを持つことが大切です。その中で、教育を通じ、自分の能力や可能性を信じ、伸ばしていけるような環境をつくり、多様な他者とつながり合いながら、幸せを感じられるようなまちを実現していくことが必要と考えております。教育行政の総合的な推進に向け、教育大綱の策定を通して、教育委員会と互いの理念を共有し、連携して区政を進めてまいります。
次に、区長の政治スタンスについてのお尋ねです。
まず、政策合意についてです。
特定の政党と私自身が具体的な政策の合意をした認識はありませんし、御指摘の記載についても把握しておりません。政党に所属する方々が、私の政策に共感、賛同していただいたことを記載したものと理解しており、その内容について申し入れることは適当ではないと考えます。
次に、区長の退職金カットについてのお尋ねです。
港区特別職報酬等審議会条例において、退職手当の額の見直しについては、あらかじめ、港区特別職報酬等審議会に意見を聞くと規定していることから、私の任期における退職金に限定して適用する特例条例の制定に当たっても、諮問の必要性について検討しております。条例の議会への提出は、検討の状況により、私の任期中の適切な時期にいたします。
次に、平和観と憲法改正についてのお尋ねです。
区の平和に対する姿勢は、港区平和都市宣言に集約されているものと考えております。当然に、首長である区長としての平和観も同様です。引き続き、区民とともに、世界の恒久平和及び核兵器廃絶に向けた取組を進めてまいります。憲法改正については、国の責任において広く国民の合意を得てなされるべきものと考えております。今後も憲法を尊重しながら区政を推進してまいります。
最後に、夫婦別姓についてのお尋ねです。
夫婦別姓については、国において、婚姻制度等の見直し審議が行われ、平成8年に民法の一部を改正する法律案要綱が答申され、選択的夫婦別姓制度の導入が提言されました。答申では、子どもの氏の考え方や変更の方法等についても触れられていますが、民法の改正法案の国会提出には至っていません。国は、国民の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえて、さらなる検討を進めることとしています。
世界で夫婦同姓を義務づけているのは日本だけであり、国際連合から法改正すべきという勧告を受けている点なども踏まえ、子どもの観点も含め、検討を加速すべきと考えます。よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。
○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団を代表しての土屋準委員の総括質問に順次お答えをいたします。
最初に、小中一貫教育についてのお尋ねです。
教育委員会では、平成24年度から、中学校通学区域の幼・小・中の教員で組織をするアカデミーを立ち上げるとともに、小中一貫教育校の開設により、教育課程の連続性を確保し、学力の向上や豊かな心の育成などを図ってまいりました。今後、教育委員会は、事務局内に立ち上げたプロジェクトチームで、これまでの小中一貫教育の成果を確認してまいります。また、中高一貫教育の検討を進めていく中で、区として望ましい小中一貫教育、中高一貫教育の在り方について明らかにしてまいります。
最後に、国際理解教育についてのお尋ねです。
教育委員会では、国際理解教育を重点的な施策として、区独自の先進的な取組を進めてまいりました。小学校の国際科、中学校の英語科国際の授業、ネーティブティーチャーの常駐派遣など、長年にわたる取組は学校に定着し、確かな英語力向上につながっております。来年度以降は、これまでの成果を踏まえ、英語によるコミュニケーション能力の向上、異文化に触れる体験、自国の歴史や文化の理解の3つの視点で、港区ならではの国際理解教育を体系化し、幼少期から中学校まで一貫した国際理解教育プログラムを構築することで、国際社会で活躍できる真の国際人の育成を図ってまいります。
よろしく御理解のほど、お願いをいたします。
○委員(土屋準君) 何点か再質問をさせていただきます。
最初に、この羽田空港機能強化についてです。これは神宮外苑再開発のほうにも共通するのですけれども、区長は反対したことはないとの答弁でしたが、このホームページ、これを見た方から、区長選挙前の出馬会見の前に、このホームページが、反対していますとこう書いてあったのが、文言がその後ごっそり消えていたというふうに言われておりましたし、また、当時の清家区議のホームページとして、これはXで出回っていたものがこちらです。このように、反対していますというふうに書いてあります。
羽田新経路の質問では、その反対していたのを姿勢が変わったのかということを聞いておりますので、その点をお答えいただければというふうに思います。
それから、この神宮外苑再開発のほうです。このようなことに加えて、御本人も、このような発信をXでされていますけれども、これを見ると、とにかくその発信そのものが誤認されやすいのではないかと思います。この内容を見ると、このユネスコの諮問機関からの提案のことを言っているのですけれども、それを紹介することによって、これは個人の取組なのか、これは区民に誤認されやすい、そういった投稿なのではないかと思います。
それから、この次は、これは反対デモのことが書いてありますけれども、今日の反対デモには参加できませんでしたとあるということは、反対をしたいという、そういう意思表示ではないかと思われます。
こうしたふうに書いていながら、また、反対派と連携して区議選及び区長選挙の支持を得ておきながら、それは知りませんでしたとか事実誤認でしたというようなことは、区民をだましているのではないかというふうに感じざるを得ないのであります。
武井前区長の時代から、この4列のイチョウ並木はもともと残る予定であって、区道に18本のイチョウは移植し、保全されるという計画です。これは武井区長のときから決まっていることであって、現区長がそれを引き継いでいるにすぎないと思います。しかし、これまでの清家区長の区議会議員時代の行動から、清家さんが区長となったことで実際に区道の18本のイチョウもそのまま残ると思っている区民の方もいるようです。
そこで、これに対する再質問は、区議会議員時代と、区長選挙の直前から神宮外苑再開発に対する方針、考え方を変えたのかという質問ですので、再度お答えをお願いいたします。
それから、その神宮外苑の説明会の要請です。区長は誰にでもオープンで対話型の説明会をと区議会議員時代から言われておりましたけれども、先日行われた説明会では、区長が区長選挙で連携し、それをともに求めてきた党や団体から、納得いく説明会ではなかったと言われております。また、区長選挙当選後も、きちんとした説明がないまま進めることは絶対あってはいけないと、テレビのインタビューでも答えております。
そうすると、新たに求めないということですと、本当に何ら、武井前区長と変わっていないのではないかということになります。そうすると、先日行われた説明会でよいと判断し、今求める状況ではないということでよろしいのか、あるいは再度、状況によるということですけれども、再度説明会を求めるようでしたら、計画を止めること、少なくとも遅らせることになると思いますので、それは矛盾しているのではないかと思います。
この計画を止めるつもりではないということなのか、お答えをいただきたいと思います。
それから、(2)の公共施設管理者同意については、これは今後も何ら変更は生じないということでよろしいのか、確認のため、もう一度答弁をお願いいたします。現時点に限らず今後もかということです。
それから、事務事業評価による財源確保についてです。この50億円という公約がどこに行ったかということを聞いておりますので、それに触れられていませんでしたけれども、要はその50億円というのは、もう触れないということで取下げということでよいのか、そこのところを答弁お願いいたします。
それから、港区平和都市宣言についてです。その拡大したいということで変更するのならば、刊行物を減らすというのは逆方向になるのではないかというところです。10月1日から削減すると言っていたのが、変更することになったようですけれども、それがどうしてなのかというところを教えていただければと思います。
それから、政策合意についてです。区長はその政策合意を把握していないと言っておりましたけれども、これは、区長の投稿ですが、5月28日の時点ということは定例会の前の時点ですけれども、定例会で把握していないと言った前の時点でこういうことがあったということですから、把握していると思うのですが、その辺の整合性はどのように考えるのか、お伺いをいたします。
それから、先ほどのその文書は虚偽であるという認識でよろしいか、虚偽の記載をされたなら訂正を求めるのか、求めることはしないのかということですけれども、虚偽だというのなら、やはり訂正を申し入れるべきではないかと思いますが、その辺の答弁をお願いいたします。
ということで、羽田空港、神宮外苑再開発から始まって、それからもう一つ、先ほどの合意の内容ですけれども、政党の後援会ニュースには、確認・合意をしたことを踏まえるとなっているわけでございます。一応こうなっていることですので、それに合わせた答弁をお願いしたいと思います。
以上ですが、いずれにしても、反対していたのではないかという問いに、区長としての立場とか、少し違う答えになっておりますので、ぜひ質問に即した答弁をしていただきたいと思います。
以上です。よろしくお願いします。
○区長(清家愛君) ただいまの自民党議員団、土屋準委員の再質問に順次お答えさせていただきます。
まず初めに、事務事業評価による財源確保についての御質問です。事務事業評価などによる財源確保についてですが、50億円を目指して、ただいま様々な分野、観点から、事業のスクラップ・アンド・ビルド、新しい事業を始めるための財源確保に向けて、方向性を含め、部署横断的に総合的な観点から議論を進めているところです。
次に、港区平和都市宣言の刊行物への掲載についての御質問です。港区平和都市宣言の刊行物への掲載につきましては、より効果的な発信ができるようにという思いで検討しておりましたが、様々な御意見をいただいたことも踏まえまして、より効果的な発信をしていくためにどのように掲載すべきかどうかという点について、検討を深めてまいりたいと思っております。
次に、神宮外苑再開発事業についての区長のスタンスについての御質問です。神宮外苑再開発事業につきましては、一貫して住民との対話を求めてまいりました。事業者に対して多くの区民等に共感を得られるまちづくりを行うように、今後も強く求めてまいります。
次に、公共施設管理者の同意についての御質問です。公共施設管理者の同意につきましては、令和4年3月10日に決定した都市計画の内容と整合が図られることを確認しておりますので、協議回答書の記載の事項に変更は生じないと認識しております。
次に、説明会の要請についてです。説明会につきましては、先ほど御答弁させていただいたとおり、状況に応じて説明会の開催を求めてまいります。今回の説明会の開催方法等について、これまでの区の要請と違った点につきましては、また、その状況に応じて、そうした手法も含めて要請を行ってまいります。
次に、羽田空港機能強化についての御質問です。羽田空港新経路について、固定化回避を一貫して求めてまいりました。港区の上空が飛行経路になっていることについて、望ましいことではなく、この点について一貫して主張してきております。区民の生活を守るという立場から、引き続き国に対し固定化回避を強く要請してまいります。
次に、区長の政治スタンスの政策合意についての御質問についてです。こちらにつきましては、私は区民の幅広い声をお聞きするために、政党関係者の方を含めて全ての方のお問合せにお答えをしてまいりました。私自身の政策に共感し賛同していただいたことを記載されたものと理解をしており、その内容に対して私が申入れをすることについては、適当ではないと考えております。全ての政党関係者を含め、全ての方のお問合せについてお答えをしてきており、私自身の政策に共感し賛同していただいたことから自主的に応援していただいたものと理解しております。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○委員長(池田たけし君) 区長、再質問の趣旨でございますけれども、神宮外苑再開発についてと、羽田空港新経路について、御質問の趣旨に沿ってお答えいただけますか。
○委員(土屋準君) 言っていたことが変わったか、変わっていないかということです。
○区長(清家愛君) 神宮外苑再開発事業につきましては、これまでも、区民との対話によったまちづくりについてを一貫して求めてきております。事業そのものについてよりも、区民の声をしっかりと聞いて、そして説明責任を果たし、そしてそれが可能な限り反映されるまちづくりというものを求めてきております。そして今後も、区長として事業者に対して多くの区民などに共感が得られるまちづくりを行うよう強く求めてまいります。
羽田空港新経路の固定化回避につきましても、これまでも区民の立場から、この港区上空を飛ぶその新経路について、このルートの固定化についての回避を求めてまいりました。そして、今後も区民の生活を守る立場から、そしてこの固定化回避の早期実現を要請してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○委員(土屋準君) いろいろ再質問しましたが、なかなか質問の趣旨と違うところが多くて、主なところは反対していますと区議時代に言っていたのが変わったかどうかという質問だったのですけれども、なかなか的確な答弁がありませんでしたので、また今後は、次の定例会なり、また別の機会に取り上げさせていただければと思います。いずれにせよ、この武井区政20年の振り返りもしましたけれども、本当にこの港区はこの20年で大きく進展したなというふうに思っております。
清家区長に替わったわけですけれども、選挙では、区長の姿勢に大いに期待をした区民も多かったと思いますが、この細かいところを見てみると、なかなか数字が出てきたのがなくなったり、あるいは態度が不明確なところがあったりしますので、ぜひそういった区民の声とか期待には、ぜひ誠意を持って向き合っていただければと思います。
以上で質問を終わります。