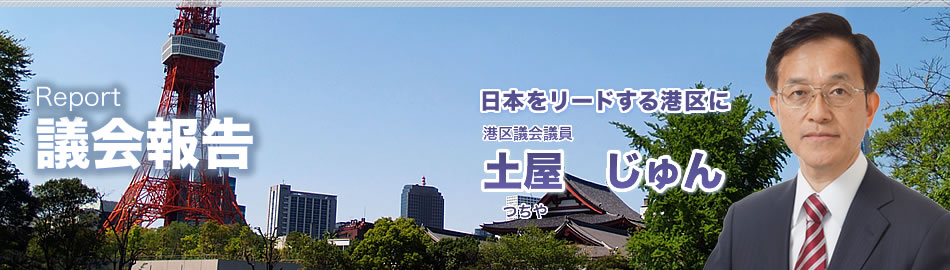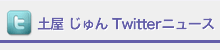○委員(土屋準君) 教育費におきましては、非認知能力を伸ばす教育についてお伺いいたします。
IQや学力といった、テストなどで評価している能力を認知能力といい、物事に対する考え方、取り組む姿勢、行動など、日常生活、社会活動において重要な影響を及ぼす能力を非認知能力というそうです。
非認知能力が重要視されるきっかけとなったのは、ノーベル経済学賞受賞者のジェームズ・J・ヘックマンらの研究チームが、幼児期の特別な教育が及ぼす影響について、社会的リターンをもたらしている要素は、IQテストで評価されてきた能力、すなわち認知能力ではなく、IQテストで評価されてきた能力以外の能力、すなわち非認知能力であるとして、幼児期に非認知能力を育成することの重要さを経済学の立場から示したことです。この研究発表により、世界各国で非認知能力に焦点を当てた様々な研究が行われるようになりました。
OECDいわゆる経済協力開発機構では、2015年に非認知能力の定義を公表し、PISAと呼ばれる国際的な学習到達度に関する調査にも反映しております。
日本では、各省庁がそれぞれの観点から、新しい時代に求められる能力概念の定義を行っており、その定義には、非認知能力と解釈できる要素が多く含まれております。
文部科学省は、新学習指導要領の育成すべき資質・能力の3つの柱として、1つ目が知識及び技能、2つ目は思考力、判断力、表現力など、3つ目が学びに向かう力、人間性など等で非認知能力育成の重要性を説き、能力向上の取組を進めています。
経済産業省においては、社会人基礎力を提唱するほか、非認知能力成長支援サービスの実証や導入に補助金を交付するなど、官民が連携した動きも加速しています。
一方で、非認知能力にはいまだ学問的に統一された見解がなく、様々な団体がそうした現状を踏まえ、研究を進めてきています。
そこで質問ですが、港区では現在、非認知能力を伸ばす教育についてどのように取り組んでいますでしょうか。
○教育指導担当課長(清水浩和君) 教育委員会では、非認知能力を、問題を解決する力、忍耐力や自制心、協働性、コミュニケーション力と捉え、幼児・児童・生徒の育成に努めております。具体的には、幼児期において、遊びの中で試行錯誤しながら考えを工夫したり、友達と関わる中で互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的に向けて協力したり、充実感を持って行動する活動に取り組んでおります。
また、小学校では、生活科や総合的な学習の時間をはじめ、各教科で子ども自身が問いを立てて解決方法を考え、仲間と協働して学びを進めていく、探求的な学びに取り組んでおります。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。港区でも様々な取組をしていることと思います。
そこで質問ですけれども、非認知能力を伸ばす教育というのはこれからも重要になってくると思いますが、どのように考えますでしょうか。
○教育指導担当課長(清水浩和君) 幼稚園、小・中学校では、知識・技能などに関わる認知能力だけでなく、他者とコミュニケーションを取る力や、何事にも意欲を持って取り組む力などについても重要な非認知能力と考えており、幼稚園から中学校に至る12年間で、子どもたちの学びに向かう力や人間性を育む教育を進めてまいります。
今後は、非認知能力に関する研修を副校園長研修会で実施するなど、教員研修を通して非認知能力についての教員の理解を深めてまいります。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。
この非認知能力を伸ばす教育というのはこれからますます重要になってくると思いますので、ぜひいろいろな工夫をして取り組んでいってもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。