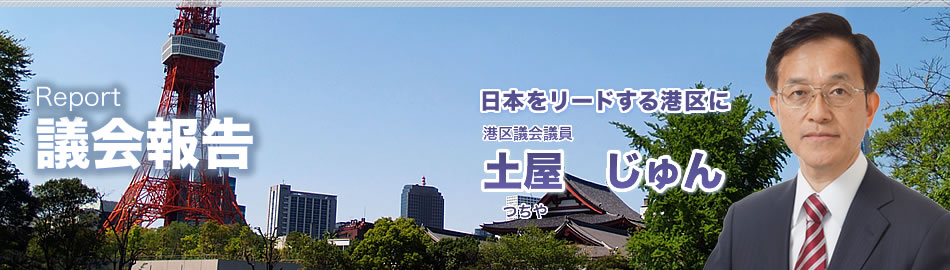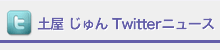○委員(土屋準君) 総務費におきましては、まず、港区版ふるさと納税制度の方向性について、お伺いいたします。
港区版ふるさと納税制度は、自ら寄附先を選択し地域を応援するというふるさと納税制度本来の趣旨を踏まえ、返礼品によらず、寄附者自身が寄附の使い道を選び、区の取組を応援してもらうという制度です。寄附の活用先は、港区が実施する各分野の取組、基金を設立している取組のほか、区政全般や団体応援寄附金といったものがあります。これに対しては、港区も返礼品を設けるべきだという意見もありますが、本来のふるさと納税制度の趣旨から離れた返礼品合戦に港区が参戦するのかと言われることもありますので、好ましくないという考え方もあります。
そこで、以前から取り上げておりますが、例えば東京湾大華火祭といったある特定の事業を企画し、ふるさと納税の寄附の活用先にするということも考えられないかと思っております。このような事業は開催経費も多額になり、その経費を捻出するのも大変ですが、ふるさと納税制度を活用すれば、多くの寄附を集められる可能性があるのではないかと思っております。
以前質問した際には、区は、令和元年度まで全ての子どもに居場所と学びの環境を整えるですとか、MINATOシティハーフマラソンを盛り上げるなど特定の事業を寄附の活用先としておりましたが、令和2年度からは、活用先を特定の事業に絞らず、各分野への取組に拡大しておりますということで、港区ならではの魅力的な寄附の活用先となるよう、見直しや拡充に取り組んでまいりますという答弁でございました。
そういったことでしたので見直しもあるかと思いますが、そこで質問は、東京湾大華火祭のような特定の事業を企画し寄附の活用先にするということについて、現在どのように考えていますでしょうか。
○企画課長(相川留美子君) 港区版ふるさと納税制度については、令和2年度から活用先を各分野への取組に拡大するとともに、活用を予定する具体的な取組について、区のホームページなどで紹介しております。今年度は、放送100年を契機とした観光振興事業や子どもの意見反映推進事業などタイムリーな取組を予定しており、寄附が増える年末に向けてSNSなどを活用した積極的な周知を行ってまいります。また、今年度から新たに国際化を分野別の寄附の活用先として設けるなど、取組の見直しや拡充も行っております。
引き続き区の魅力を高め、区を応援したいと思っていただけるよう、必要に応じた寄附の活用先の見直しや拡充に努めてまいります。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。見直しも随時されているようですが、続きは総括で取り上げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、基本計画のサイクルについて、お伺いいたします。
区長は、基本構想の見直しを掲げていますが、実際の区政は基本計画を指針として運営されていると思います。よって、この基本計画の改定というのが重要になってくるのではないかと思います。基本計画は現在6年の期間とし、中間の3年で後期見直しをしています。改定に当たっては、区民や在勤者・在学者で構成されるみなとタウンフォーラムからの提言を受け、議会の質疑を経て改定されています。また、各地区総合支所が、区民参画組織等からの提言を踏まえて見直す地区版計画書も併せて改定されています。
そこでまず質問です。現在の基本計画、地区版計画書の改定はどのようなサイクルで行われていて、現在の形になったのはいつからでしょうか。また、他区の状況はいかがでしょうか。
○企画課長(相川留美子君) 港区基本計画と地区版計画書のサイクルにつきましては、3年ごと見直しを行うこととし、策定または改定から2か年度目に区民参画において提言をいただき、3か年度目に計画の素案を公表し、パブリックコメントを経て計画を決定しております。
計画期間につきましては、平成15年に港区基本計画を策定した際に6年とし、3年目に見直しを行っております。その後、平成21年に地区版計画書を新たに策定し、現在の計画の仕組みとなっております。
他区の状況につきましては、杉並区が港区と同様に3年目に見直すこととしていますが、計画期間は9年となっております。特別区全体の傾向としましては、計画期間を10年としている区が最も多く、見直し期間を設定している区もあれば、明確に定めていない区もある状況となっております。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。他区は比較的長い期間が多いようですが、6年の期間と港区は言っても、中間の3年で後期見直しをするということになりますと、実際3年ごとに見直しのサイクルが回ってくるということで、丁寧ではありますが、業務が多忙になるのではないかということも考えられます。政治過程の観点からすれば、計画期間は、考え方として区長の任期である4年とすべきではないかという考え方もあります。選挙により区民の信託を受けた区長が公約実現のために基本計画を策定すべきであって、そのためには計画の期間は区長の任期に合わせるべきではないかという考え方のものです。
そこで、中間の見直しをしない代わりに期間を4年とする案も考えられます。一方、そうすると計画期間のサイクルは継続的なものですので、区長の任期に合わせるのはタイミングが難しいという問題も考えられます。
そこで質問です。基本計画のサイクルの変更については、どのように考えますでしょうか。
○企画課長(相川留美子君) 現行の港区基本計画は、計画期間の中間年である3年目に見直しを行ったことで、変化の早い社会動向の中でも直面する課題に対して的確に施策を講じることができていると考えております。一方で、他自治体と比較しても見直し期間が短いため、改定作業に必要となる職員や費用の負担は大きく、また、計画の達成状況を評価する政策評価の際には、対象となる期間が短いため今後の見通しを立てづらいといった課題があります。
今後、港区基本構想の見直しを進める中で、効果的かつ効率的な計画行政を推進できるよう、土屋委員御提案の計画期間の変更も含めて、改善を検討してまいります。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。この件については、また別の機会に取り上げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、総合支所長専任化の課題について、お伺いいたします。
現在の総合支所制度においては、日頃から地域の課題に向き合っている総合支所長が、地域の実態を政策形成に反映できるよう、支援部長を兼務しております。それに対して、総合支所長は兼務ではなく専任化させるべきではないかという意見も出されております。
そこで、総合支所長を専任化させる場合の課題について、2通りの方法で考えてみたいと思います。1つ目は、部長級職員を増員するということです。総合支所長は5人いますので、専任化により部長級職員を5人増員するという案でございます。
そこで質問です。スクラップ・アンド・ビルドという考え方もある中、部長級職員を増員することについて、どのように考えますでしょうか。
○区役所改革担当課長・連携協創担当課長兼務(野々山哲君) 総合支所制度が浸透し、地域との連携が深まる中、地域の顔として総合支所長に求められる役割も大きくなっており、政策課題の解決に当たる支援部長との兼務による対応が必ずしも十分でないと考えております。総合支所長が十分にその役割を担うことができるようにするために、区役所組織全体の総合的な観点から、部長級のみでなく、課長級を含めた管理職全体の配置の視点も併せて、より効果的・効率的な体制について検討してまいります。
○委員(土屋準君) 2つ目の方法です。部長同士を兼任させるという考え方があります。部長級職員を増員せずに総合支所長を専任化するとなりますと、今度は部長同士を兼任させるということになります。そうすると、業務の偏りが生じる可能性もあります。現在、兼務者は総合支所に週2回の午後勤務をしていて、あとは本庁舎で勤務しているそうです。土日は地域の行事などが多いですので、それだけで単純に計算できませんが、勤務時間から考えると、部長同士の兼任者の方が相当業務量が増えるのではないかと思われます。総合支所長にはこれまでの地域の区民との長い関わりを重視する観点もあり、給料は下がるが経験豊富な再任用職員を充てるという案も考えられますが、再任用制度自体が変わってくるところの意味はなくなってしまいます。
そこで質問です。部長同士を兼任させるということについて、どのように考えますでしょうか。
○区役所改革担当課長・連携協創担当課長兼務(野々山哲君) 部長級職員の配置に当たっては、区役所組織全体の体制の中で総合的な観点から判断されるべきものと考えております。総合支所長の配置の在り方につきましては、総合支所長をはじめ、総合支所及び支援部双方の立場の意見を聞きながら人事部門等と連携し、想定されるあらゆる形について丁寧に検討いたします。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。結局これは区長に聞かないと、どうするのかということは分からないと思いますので、続きはまた総括で取り上げられればと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、女性管理職の割合について、お伺いします。
区長は、女性管理職の割合50%実現を目指し、任期4年間での達成を目指すとしております。そこで、まず質問です。現状は、管理職は何人で、そのうち女性は何人でしょうか。
○人事課長(茂木英雄君) 令和6年4月1日現在、管理職は102名おり、そのうち女性管理職は19名となっております。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。管理職は102名で、そのうち女性は19名ということは、男性は83名ということになると思います。現在の管理職の定数から、4年間で女性管理職の割合を50%にするとなると、私も計算してみたのですが、単純に64名分の管理職ポストを増やして女性に充てる方法や、32名の男性の分を女性に充てることになると思います。
そこで、様々な方法について考えてみたいと思います。これもスクラップ・アンド・ビルドの考え方もある中ですが、管理職ポストを64名分増加させるということはできるのでしょうか。
○人事課長(茂木英雄君) 組織内での必要性に応じ管理職ポストに増減が生じることはありますが、現時点で単純に64名分の管理職ポストを増加させることは難しい状況にあると考えております。今後、民間専門人材等で新たなポストを設置することも含めて、取組を検討いたします。
○委員(土屋準君) 分かりました。
それでは次に、内部から女性のみを昇進させるということはできるのでしょうか。また、例えば女性であることを条件として任期付職員などを公募するといったことはできるのでしょうか。
○人事課長(茂木英雄君) 公平性の観点から、女性職員のみを管理職へ昇任させることや、女性であることを条件として任期付職員を公募することはできません。
○委員(土屋準君) そうですね。区長は、民間人材の活用や人事交流などによる外部人材の管理職登用等も視野にしているようでございます。
そこで質問です。この4年間で男性の管理職32名を外部に放出し、女性のみを新たに外部から登用することはできるのでしょうか。
○人事課長(茂木英雄君) 男性の管理職から退職や降任の意向などがない限り、4年間で男性管理職32名分の管理職ポストを充てることはできません。また、女性であることを条件として、外部から新たに管理職を登用することはできません。このため、テレワークの推進やフレックスタイム制の導入検討、ポストの創設など、様々な手法により、女性が働きやすくキャリアアップを望める環境を整えていくことで女性管理職増員を目指してまいります。
○委員(土屋準君) ある程度の増員はできるでしょうが、どの方法を取っても50%を4年間でというのはなかなか難しいのではないかと思いますが、続きは総括でお伺いさせていただければと思います。
次に、防災についてお伺いいたします。まず、災害対策職員住宅についてです。
港区では、夜間・休日等の職員の勤務時間外に災害が発生し、またはそのおそれがある場合に、初動態勢である職員の指揮監督を行う要員を確保するため、災害対策用職務住宅が設置されていて、防災危機管理室長、防災課長、都市計画課長が輪番制による警戒勤務に従事しているとのことです。一方、港区には、そのほかにも災害対策職員住宅が設置されております。
そこで質問ですが、災害対策職員住宅の居住職員の役割や運用体制はどのようになっていますでしょうか。
○防災課長(井上茂君) 災害対策職員住宅は、夜間や休日等、勤務時間外に災害が発生した際の初動態勢要員を確保するため区内に設置する職員住宅です。居住職員には、夜間・休日の待機態勢を取ることや港区総合防災訓練等に参加し、緊急時の行動力を高めることなどの義務を課しています。
令和6年4月現在138名の職員が居住し、震度5強以上の地震が発生した際などは特別非常配備態勢となり、指定された災害対策本部または地区本部に参集し、本部の設営など初動対応として災害応急対策業務に従事することと備えております。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。そういう態勢になっているのでしょうけれども、今年の元日には、能登半島地震が発生いたしました。元日というようなときには、現状で港区を考えますと、区内在住職員というのは少ないのではないかと思われます。
そこで質問です。災害対策職員住宅の居住職員にも輪番制が必要かと思われますが、いかがでしょうか。
○防災課長(井上茂君) 区は、地震の規模等に応じて、区内や近隣区などに居住する職員を災害時に直ちに参集できるよう、非常配備態勢を構築しております。夜間・休日に発災する可能性も想定し、災害対策職員住宅の入居者には、夜間・休日の待機態勢を取るほか、出張または私事旅行等により職員住宅を離れるときは事前に届出をすることを義務としており、輪番制と同様の効果を確保しているものと考えております。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。いろいろ考えなければならないことが多いかと思いますけれども、非常時の体制というか職員確保というのは、よく考えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
今は厳しい質問をしましたが、今度は逆で、防災宿直についてであります。
港区の管理職の皆さんは、輪番制で防災宿直に当たっておられます。ところが、宿直明けの日も通常勤務をされているということです。警察などは、宿直明けの日は非番となり、勤務には就かない日となっているようです。宿直明けの日は疲れもたまっているのではないかと思います。また、最近はリモート勤務など多様な勤務体制も取れるようになってきました。
そこで質問です。防災宿直の宿直明けの日は、休日かリモート勤務などの工夫で疲労対策ができればと思いますが、いかがでしょうか。
○防災課長(井上茂君) 区は、正規の勤務時間外に発生する災害対策基本法に規定する災害等の非常事態に対する警戒態勢を確保するため、港区に勤務する課長職以上の職員が、交代で夜間・休日に宿直または日直勤務を行っております。宿日直勤務は、労働基準法の勤務時間、休息、休日の適用を受けることのない断続的労働であることから、本来の勤務時間の終了後に従事することができ、また、翌日の正規の勤務時間を軽減することはできないものとされております。
一方で、従事している管理職職員からは、健康面で心身の負担が増加しているとの声も上がっております。本来業務である災害対応以外の業務も増えてきていることから、業務内容の整理・見直しに取り組み、宿日直の負担軽減を図ります。
○委員(土屋準君) 工夫できるところは、ぜひ工夫していただければと思いますので、よろしくお願いします。
次に、医師会の避難所巡回についての質問を予定していましたけれども、衛生費に関わることですので、また別の機会にさせていただければと思います。
次に、港区平和都市宣言についても質問する予定でしたが、これまでに質疑がありましたので質問は控えさせていただきますが、ここでは平和の概念について述べさせていただきたいと思います。
私は、平和を守るには2つの方向のことが必要だと思います。1つは、こちらから戦争を仕掛けないということです。こちらから戦争を仕掛ければ当然平和ではなくなります。もう一つは、攻められないということです。いくらこちらから戦争を仕掛けなくても、他国から攻められれば戦火にまみれることになり平和でなくなります。
このような観点から現行の憲法を見ると、一方の観点からのことは書かれていますが、もう一方の観点からのことは書かれていません。よって、このままでは平和は守れないということになります。平和を守るのか、それとも憲法の文言を守るのか。憲法改正に際しては、どちらを選択するのかということになると思いますが、続きは総括で取り上げたいと思います。
次に、女性活躍推進と性的少数者への配慮について、お伺いします。
オリンピック女子種目で、性別適合手術を受けた元男性のトランス女性が出場するということがありました。公平性をめぐる議論も起こりました。IOC国際オリンピック委員会が定める個人参加の基準を見ますと、元男性であっても男性ホルモンのテストステロン値が一定以下であれば、女子種目への参加が認められるとのことです。しかし、テストステロン値などの身体的要因の基準はまだ科学的根拠が少ないという指摘もあり、たとえテストステロン値が一定基準を下回ったとしても、男性として生きてきた期間に形成された骨格や筋肉量などで優位性があるとの疑問は残ります。元男性の出場により、五輪の出場やメダル獲得などの機会を失う女性選手が出てくるという批判もあります。
ところで、国会で政治分野における男女共同参画社会基本法の改正法が成立してから、政党に対して、男女の候補者数の目標設定や候補者の選定方法の改善、候補者の人材育成などに取り組むよう求めています。港区では、第4次男女平等参画行動計画で、審議会委員の女性委員比率を向上させたり、管理的地位、これは課長級以上ですけれども、にある女性職員の割合を向上させたりする目標を定めています。一方、厚生労働省は、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会の分科会で、就職活動などで用いる履歴書の性別欄について、男女別の選択肢を設けず記載を任意とする様式例の案を示しました。心と体が一致しないトランスジェンダーの人々の要望に応えたと言われております。
女性活躍推進の立場からすれば、公職の候補者や審議会委員、管理職員の女性の割合を高める目標を設定するなら、男女の区別を明確にする必要がありますが、性的少数者に配慮する立場からすれば、男女の区別を明確しないという矛盾のような事態が起こります。
そこで質問です。現在、審議会委員や職員の履歴書等の性別欄の男女別記載はどのようにされているのでしょうか。
○人権・男女平等参画担当課長(小坂憲司君) 審議会等における公募委員の選考や職員の採用選考においては、特定の性別を排除しない、性自認の多様な在り方に対応する等の理由から、性別欄は設けていないか任意記載としています。団体推薦の審議会等委員については、女性の意見を区の施策・方針に反映させるために、推薦元の団体に女性の推薦について協力を依頼することがあります。審議会等委員の委嘱後には、男女平等参画行動計画において女性比率の数値目標を定めていることから、統計を取るため男女を確認しております。職員についても、職員管理の観点や管理職の女性割合の目標値を定めていることから、任用時には任用履歴書に性別欄を設け、男女を記載しています。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。それぞれの部署でそれぞれの形を取っていることと思います。そうすると、結局、女性活躍推進と性的少数者への配慮のどちらを優先するのかということになると思いますが、これも総括でお伺いしたいと思います。
最後に、住民票における未届けの規制についてお伺いします。
質問も幾つか出ていましたが、長崎県大村市が、同性カップルの住民票で世帯主と同居するパートナーの続柄欄に夫(未届け)と記載するということがありました。住民票は、住民の届出などに基づき区市町村が作りますが、自治体ごとにばらばらにならないよう、住民基本台帳法で項目などを規定し、実務は総務省が技術的助言としてまとめた要領に基づいて作られています。
これまで夫(未届)、妻(未届)という続柄は事実婚、これは内縁関係ですけれども、の場合に記されてきました。この住民票を基に健康保険でどちらの扶養に入れるかなどのメリットがあります。同性パートナーについては、2018年6月の衆議院の法務委員会で、当時の総務大臣政務官が、親族関係があると言えないため同居人と記載すると答弁し、実際に区市町村では同居人とするケースが少なくないようです。ただ、同性カップルを承認するパートナーシップ制度の普及で、縁故者と記載する自治体が増えてきております。総務省の要領は、縁故者を親族で世帯主との続柄を具体的に記載することが困難な者としており、同居人より関係性が強いものとなっております。
同じところに住む同性パートナーについて、住民票に続柄をどう記載しているか。都内の状況を見ると同居人との記載がほとんどで、世田谷区や渋谷区など一部の自治体では、パートナーシップ制度を利用した場合などに縁故者の記載もできるようにしているようです。
そこで質問です。港区は現在どのようにしていますでしょうか。
○芝地区総合支所区民課長(島田晶君) 現在、区は、住民票の続柄につきまして、事実婚の場合には、夫(未届)、妻(未届)と表記しております。同性カップルの場合には、同居人と表記しております。
○委員(土屋準君) この件では、総務省見解は同性カップルについて、法律上の夫婦ではないが、準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているという前提がないと指摘しており、その上で、事実婚と同様の表記の住民票を交付すれば、公証資料である住民票の写しを交付する住民基本台帳法の適用としての実務上の問題があるとしております。
住民票は、住民基本台帳法に基づき住民の居住関係を公証する唯一の公簿で、住民票情報に基づき各種行政サービスが提供されております。事実婚は、健康保険の扶養家族に入れるなど一部の社会保障施策において法律婚と同じ扱いですが、同性カップルには適用されておらず、総務大臣は、事実婚と同性カップルの続柄を同一にすると各種社会保障の窓口で適用の可否を判断できなくなると説明しております。
そこで質問です。このような見解を踏まえ、港区は今後どのようにしていきますでしょうか。
○芝地区総合支所区民課長(島田晶君) 総務省の見解のように、同性カップルについては、住民票の続柄の表記を変更しただけでは、事実婚のように健康保険の扶養家族になるなど、社会保障制度で法律上の夫婦と同じ扱いを受けることができないなどの課題があります。また、国の事務処理要領に基づき全国統一的に事務処理を行っていることから、各区市町村の判断で続柄を決めていくことは、住民票としての公証力を損なうリスクにつながるなどという課題もあります。そのため、当事者の心情に寄り添っていくことが重要であると考えておりますが、現時点では、実施に向けて課題を整理する必要があると考えております。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。この件につきましては、状況が変わるようであれば、また質問させていただければと思っております。
いろいろな質問がありましたが、結局、区長がどう判断するかということが大きいものが多いですので、ぜひ総合的に今度質問させていただけばと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。